
法学部、経済学部、文学部、理学部、国際社会科学部がワンキャンパスで学ぶ学習院大学では、2023年度より、全学共通科目「宇宙利用論」を開講している。文理融合による複合的な学びで、宇宙利用に関わる人材育成をめざす同科目を開講した背景やそのねらい、展望について聞いた。
宇宙ビジネスの総合的な知識をもった人材を育成
5学部17学科の学生がワンキャンパスで学び、専門的な学びと分野を超えた学びを展開する学習院大学では、2023年度より、全学部生を対象とした「宇宙利用論」を開講している。宇宙利用論、「地球を含むすべての天体・宇宙空間を平和的かつ持続的に利用する方法」を考察する新たな学術研究領域の開拓をめざすものである。民間企業を中心に宇宙事業が活性化するなかで、限られた国や人材だけが関与できる「宇宙開発」ではなく、「宇宙利用」に考え方がシフトしてきている。こうした宇宙利用の際に必要な知見を学ぶのが、宇宙利用論である。
そもそもの発端、かねてより国際宇宙ステーション(ⅠSS)の「きぼう」日本実験棟で物質科学の実験を行ってきた渡邉匡人教授が、研究において、月の資源や土地を勝手に利用してよいのか?」と疑問をもち、宇宙法に造詣の深い同大学法学部教授・小塚荘一郎氏に相談をもちかけたことに始まる。同氏と共に、宇宙資源を利用するうえでどんな問題が起こり得るのか、そのために何ができるかを検討するなか、宇宙利用を学ぶための環境を整える必要性を感じ、「宇宙利用論」のカリキュラムを構築。令和4年度宇宙航空科学技術推進委託費「人文社会×宇宙」分野越境人材創造プログラムの採択を受け、2023年度に「宇宙利用論」の開講に至った。

博士(工学)。
学習院大学理学部物理学科卒業、同大学自然科学研究科博士前期課程修了。
日本電気株式会社基礎研究所主任研究員を経て、2004年より現職。
専門は物質科学。
同科目の目的は、宇宙の平和利用に向けたルール形成ができる、宇宙ビジネス・宇宙利用の総合的な知識をもった人材を育成すること。さらにその前段として、学生にまずは宇宙そのものに興味をもってもらうことにもあるという。所属学部や学年を問わず、誰でも受講ができる全学部対象の全学共通科目として開講しているのはそのためだ。
「理系分野と捉えられがちな宇宙ですが、宇宙利用を考えるうえでは、法律や文化など、人文社会からのアプローチも必要です。文系、理系にかかわらず、多くの学生に、現状の宇宙を取り巻く状況を知り、宇宙を『自分事』に捉えてもらうことがねらいです。ですから、宇宙にまったく知識のない学生の受講も歓迎しています。受講を入口に、宇宙への興味と理解を深めてほしいですね」
ゲストスピーカーを招きアクティブに学びを深める
2年目となる2024年度のカリキュラムは、前期の全13回(各105分)。カリキュラム開発に当たって、教育事業にも力を入れる宇宙ベンチャー企業・Space BDと産学連携協定を締結。共同で設計を行うほか、ファシリテーターとして授業に参加してもらっている。
「授業は、学生に主体的にアイデアを出してもらうことをめざし、教員やゲストスピーカーからの講義の後は、グループディスカッションやプレゼンテーションの時間を設け、最後は討論の結果を学生たちが発表する形式で行います。私たちが話すと上から目線になりがちなところも、Space BDの方が非常にうまく学生の興味を引き出してくださいます」

「『宇宙利用論』をきっかけに宇宙に興味をもった学生が、
継続的に学習や研究ができるしくみも整えていきたい」と渡邉教授は語る。
各講義には外部からのゲストスピーカーを招いており、北海道大樹町に宇宙版シリコンバレー「北海道スペースポート」を運営するSPACE COTANや、人工衛星開発を行うアークエッジスペース、宇宙×アートの切り口で宇宙エンターテイメントをコーディネートしているSPACETAIMENTなど、宇宙利用・ビジネス分野の第一線で活躍するさまざまな宇宙ベンチャー企業
による授業を実施する。
こうして多方面の視点から宇宙への興味を引き出し、宇宙利用を理解できる授業内容となっている。
宇宙先進国シンガポールで海外研修を実施する
さらに、2024年度からの新しい試みとして、9月には「シンガポール研修」を実施する。
「シンガポールは今、国を挙げて宇宙ビジネスやスタートアップを支援しています。国際社会で宇宙利用がどのように動いているかを肌で感じてもらうことが目的です。3泊5日で、宇宙産業、銀行、商社、旅行業などのさまざまな現地企業を訪問し、現場のプロフェッショナルから、日本企業の海外展開戦略や国際市場でのビジネス運営について意見を聞き、理解を深めます。将来のキャリア形成につなげてほしいと期待しています」
今後は、「宇宙利用論」の講義内 容をより充実させていくと同時に、 さらに対象を広げ、社会人も参加で きる宇宙ビジネス人材育成プログラ ムの開発構想もあるという。
「生活やビジネスにおいて、宇宙利用は徐々に身近になりつつあります。宇宙ルール形成に着目した人材創造は、国としても力を入れている領域です。本学でも、多方面の知見を融合し、宇宙利用に寄与する人材を輩出していきたいですね」
学生コメント
多様な切り口から宇宙開発・利用について学び、宇宙飛行士の方から実体験をうかがったことも印象に残っています。新しい発想やビジネスを生み出すためには、想像力と学び続ける力が必要であることに気づかされました。
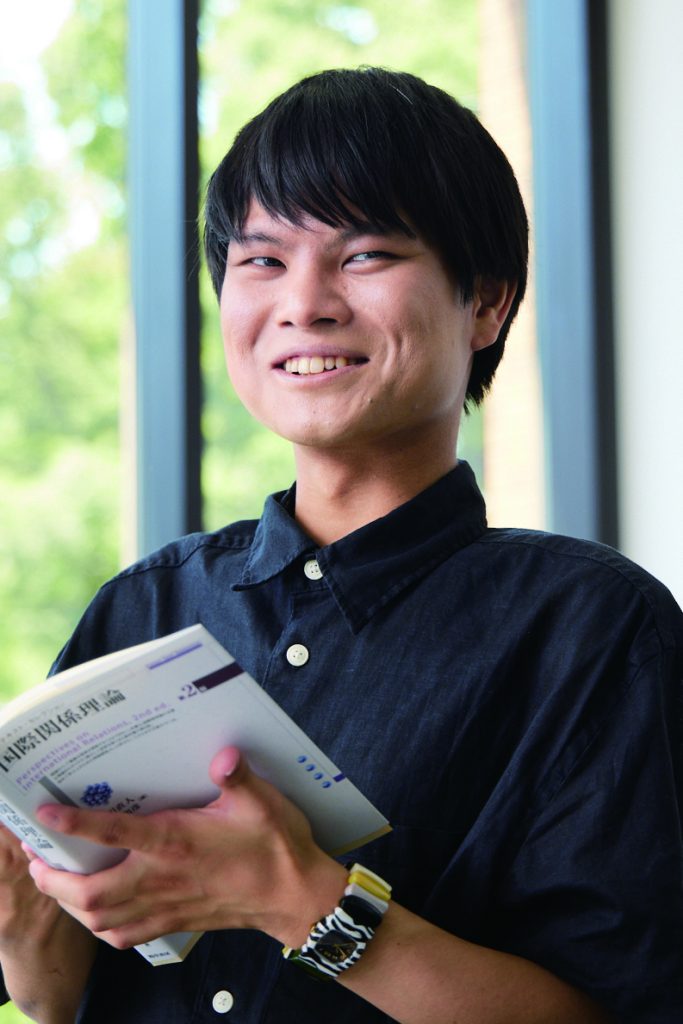
英語英米文化学科4年
出口隼詩さん
異なる学部の学生とのディスカッションを通して知識やアイデアを組み合わせ、宇宙という広大なスケールで物事を見つめた経験を通して、広い視野が養われました。得た力を就職先のゲーム会社でも生かし、エンタメ創出につなげたいです。

国際社会科学科4年
成瀬悠華さん
この記事は、日経MOOK『宇宙無限大 ビジネスのフロンティア』(日本経済新聞出版・2024年7月16日発売/監修・アクセンチュア)より転載したものです。













